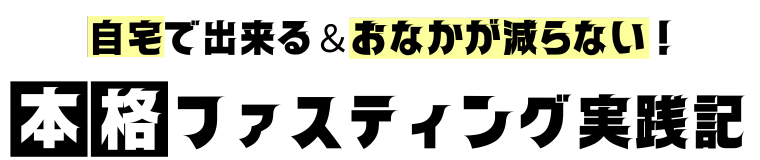アーティチョークは、チョウセンアザミという和名を持つキク科の西洋野菜です。イタリアなどの地中海沿岸で最も栽培されていますが、実は日本でも三浦半島を中心に栽培されています。
今回の記事では、
- ハーブとしてのアーティチョークの効果や副作用を知りたい
- アーティチョークの美味しい食べ方や飲み方を知りたい
- 効果のエビデンスや実例などを知りたい
これらについて、ハーブを使った最強ファスティングを定期的に実践しているハーブマニアが書いています。アーティチョークについて、他の人が持った疑問や回答なども含めて解説しているので、ぜひ読んでみてください。
アーティチョークは日本ではまだあまり知られていませんが、ホクホクした食感と、ほんのりした甘みが、病みつきになると言われていますので、ぜひ参考にして食べてみてください。
アーティチョークの基本情報

| 名称 | アーティチョーク |
| 英名 | Artichoke,Globe artichoke |
| 学名 | Cynara scolymus |
| 和名 | 朝鮮薊(チョウセンアザミ) |
| 分類 | キク科チョウセンナザミ属チョウセンアザミ |
| 原産地 | 地中海沿岸から中央アジア |
| 主要成分 | シナリン、イヌリン、トリテルペノイド、フラボノイドなど |
| 使用部位 | 若いつぼみ、葉、根 |
| 効能 | 含まれるポリフェノールによるアンチエイジング効果、整腸効果、肝臓の機能強化、胆汁分泌の促進、肝臓の解毒など |
| 禁忌、注意事項 | ・胆石がある人は注意 ・腎臓に負担がある人は注意 ・キク科のアレルギーがある人は控える |
| 利用法 | ・サラダにしたり、パスタやグラタンに入れたりして食べる ・ハーブティーとして飲む |
アーティチョークは、キク科の植物で若いつぼみの部分を食用として使用します。
ポリフェノールが豊富なのでアンチエイジング効果が期待できます。それ以外にも、整腸効果や血糖値の抑制効果も期待できます。ただし、胆石がある人、腎臓に負担がある人、キク科のアレルギーがある人は注意が必要です。
メディカルハーブとしての使い方以外にもパスタやグラタンに入れて食べると美味しいですし、ハーブティーが一般的な使い方です。
アーティチョークの効果・効能・作用を解説
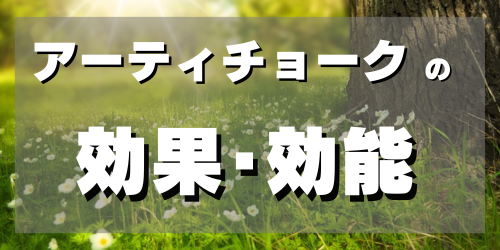 アーティチョークに期待される効果として代表的なものに
アーティチョークに期待される効果として代表的なものに
- アンチエイジング効果
- 食物繊維による整腸効果
- 血糖値上昇抑制効果
があります。また、これら以外にも期待される作用などがあるので解説します。
効果①:アンチエイジング効果
アーティチョークにはアンチエイジング効果が期待されますが、その理由は「シナリン」や「アントシアニン」「ケルセチン」「ルチン」などの含まれるポリフェノール類が含まれるからです。
そして、ポリフェノールには、抗酸化作用があります。
抗酸化作用とは、細胞を錆びさせる活性酸素の発生や活動を抑制する機能のことで、ポリフェノールを摂取することにより、抗ガン作用やアンチエイジング効果が期待できます。
さらに、「シナリン」には、胆汁の分泌を促進して消火を助けたり、コレステロールを下げる効果があると言われています。
効果②:整腸効果
代表的な効果の2つ目は整腸効果ですが、アーティチョークには、「イヌリン」などの水溶性食物繊維が含まれています。そして、これらには主に腸を整える効果があります。
どのような作用があるかというと、腸に到達するまでに食物繊維が水分を吸収して膨らみ、お通じを促します。そして、腸の中で発酵するので腸内の善玉菌が活動しやすい環境を作るのです。また、それだけでなく、余分な糖分や脂肪分を吸着し身体の外に排出します。
以上の働きにより、水溶性食物繊維が腸や身体全体に健康的な影響を与えるとされています。
効果③:血糖値上昇抑制効果
代表的な効果の3つ目は、血糖値上昇抑制効果ですが、アーティチョークに含まれるクロロゲン酸の効果です。
クロロゲン酸は、コーヒーなどにも含まれる物資で、先ほど出てきた「シナリン」などと同じくポリフェノールが多く含まれ、抗酸化作用が期待出来ます。
さらにクロロゲン酸には、血糖値の上昇を抑えがあります。食事などで身体の中に入った炭水化物や糖分は、体中で糖質分解酵素により細かく分解され、血流に乗って全身の細胞に届けられます。
クロロゲン酸には、糖質分解酵素の働きを阻害し、血糖値の上昇を抑制する効果があると言われています。このため、クロロゲン酸には、血糖値上昇が引き金となる、糖尿病などの生活習慣病に対する抑制効果が期待されています。
その他の効果・作用
アーティチョークには、代表的な3つの効果以外にも様々な効果や作用があります。
利尿効果や肝臓の解毒、動脈硬化症、糖尿病の改善、脂肪の分解や二日酔いにも効果があります。
アーティチョークの副作用や注意事項、禁忌など
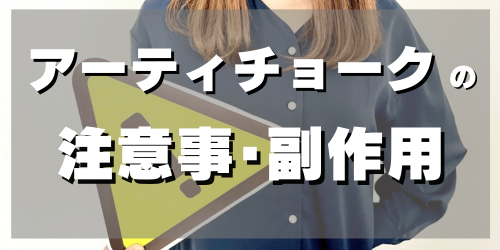 アーティチョークは、一般的な量を食用として摂取する限りでは、妊娠・授乳に悪影響を及ぼしません。
アーティチョークは、一般的な量を食用として摂取する限りでは、妊娠・授乳に悪影響を及ぼしません。
しかしながら、胆汁の分泌を促進する影響で、胆石がある人は避けた方がいいと言われています。また、アーティチョークに含まれるカリウムが腎臓に負担をかけるため、腎臓に負担がある人は避けた方がいいでしょう。
さらに、キク科の植物に含まれる「セスキテルペンラクトン」「シナロピクリン」には、鼻炎や気管支炎、蕁麻疹などのアレルギー反応があることが報告されているため、キク科の食物にアレルギーのある人は食べるのを控えた方が良さそうです。
アーティチョークのハーブとしての使い方
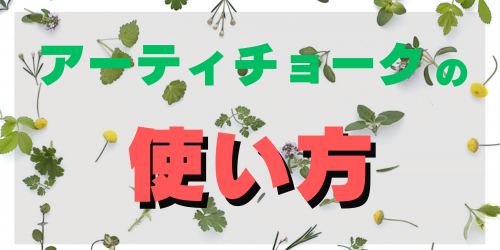
アーティチョークのレシピ、食べ方やティーの入れかた飲み方など
1 食べる
まず、まるごと茹でるか蒸しましょう。
アーティチョークを丸洗いし、トゲが残るガクの先端をハサミで切り落とし、20~40分ほど茹でるか蒸して柔らかくします。
柔らかさの目安として、串がすっと刺すことを目安として下さい。茹でるときは、レモン、またはお酢と塩を加えると、えぐみが取れます。
柔らかくなったら、ガクを1枚1枚はがしていきます。ガクをすべて剥がした後、縦にカットします。ワタ(花びらの部分)はすべて取り除きます。そして、ホクホクの食感が味わえる、芯の部分を切り取りましょう。
切り取った箇所は変色しやすいため、お酢かレモン汁を付けておきます。そして、ガクの付け根の肉厚な部分を、マヨネーズやオイル系のソースを付けて、歯でこそぎ取るようにして食べるとおいしいです。
また、フードプロセッサーに入れて混ぜてディップソースにしたり、ピザの具材にするのもおすすめです。
2 お茶として飲む
よく洗った食用のアーティチョークの蕾を、まるごと鍋で水から煮て、弱火で1時間沸騰させた後、4~6時間浸したままにしておきます。
その後、アーティチョークを除けば完成です。アイスでもホットでも楽しめますし、蜂蜜・レモン・ローズマリーを入れても美味しいです。
アーティチョークのよくある質問
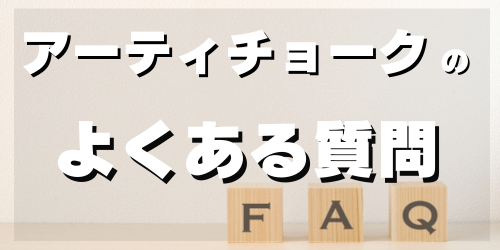
はい、されています。
ただ、日本には江戸時代にオランダから渡来しましたが、それほどポピュラーな食物にはなりませんでした。
アーティチョークは高さ1.5~2m、葉の大きさは50~80cm、つぼみの大きさは8~15cmです。花の大きさは直径15~20cmと大きく、花びらは細かく、アザミの花のような見た目をしています。花の色は、青味がかった紫色です。
アーティチョークの植え付け時期について、夏と冬は避け、春か秋の、暑すぎず寒すぎない時期を選びましょう。
アーティチョークは多年草で大きくなるため、複数植え付ける場合は60cm以上間隔を取ってください。鉢やプランターで育てるときは、必ず10号以上を選びましょう。
土については、酸性土壌を嫌うため、植付前に苦土石灰をすき込んでから、腐葉土を混ぜ込みましょう。市販の野菜用培養土でも代用できます。
アーティチョークは多湿を嫌うため、表土が乾燥し、白っぽくなってから、水やりをしましょう。また、肥料を与える必要はありません。
アーティチョークのつぼみは、春、気温が上がり始める頃に大きくなってきます。5~6月頃、つぼみの大きさが10~15cmとなり、開花直前となった頃に収穫します。
まとめ

アーティチョークのレシピ、食べ方やティーの入れかた飲み方など
アーティチョークの歴史・起源・由来
アーティチョークは地中海地方原産の多年草です。
元々は野生のアザミでしたが、ギリシャ・ローマ時代から品種改良がなされた結果、今の姿になりました。
本格的に栽培が開始されたのは、15世紀のイタリアからです。その後徐々にヨーロッパ全体に伝わりました。特に、16世紀にフランスに伝わった原因として、フィレンツェのメディチ家からフランス王家に輿入れしたカトリーヌ・メディシスが、当時媚薬とされていたアーティチョークを、結婚初夜に食べ過ぎた逸話が伝わっています。
日本には、江戸時代にオランダから渡来しましたが、それほどポピュラーな食物にはなりませんでした。
研究情報(エビデンス)
下記の研究データ、エビデンスを参考にさせて頂きました。
乳酸菌を多く含むアーティチョークを1日あたり180gの量で15日間摂取させた男女20人の便秘症状を抱える参加者について、アーティチョークを摂取したグループでは有意な症状の緩和が観察されました。アーティチョークは、便秘患者にとって有益な効果が期待されます。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22225544
この研究では、アーティチョーク葉エキスを含む植物療法が機能性胃腸障害の症状を改善する可能性があることが示されました。311人の患者を対象に60日間の観察を行い、症状の重症度が有意に減少し、全体的な臨床的な反応も観察されました。また、薬物治療に比べて肝機能や血液脂質にも良好な影響があることが示唆されました。アーティチョーク葉エキスを含む植物療法は機能性胃腸障害の管理において有望な選択肢であり、追加の研究が必要です。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20485248
アーティチョーク葉エキスは、高コレステロール血症の成人において血漿コレステロールを有意に低下させることが示されました。75人の被験者を対象にした試験で、治療群では平均4.2%の改善が観察されました。この研究は、アーティチョーク葉エキスのコレステロール降下効果を支持するデータです。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18424099/
この研究では、便の重量と大腸がんのリスク、および非デンプン多糖類(食物繊維)の摂取との関係が明らかにされました。世界の20の地域で行われたデータ分析により、便の重量が大腸がんのリスクと逆相関関係にあることが示されました。また、食物繊維の摂取量と便の重量の間にも正の相関関係があることが明らかになりました。食物繊維を多く含む食事は、便の重量を増やし、大腸がんのリスクを低減する可能性があります。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1333426/
この研究では、EPIC-Oxfordコホートの男女20,630人を対象に、栄養やライフスタイル要因と腸の運動頻度の関係を調査しました。結果として、ベジタリアンやビーガンの人々は、肉食者に比べて腸の運動頻度が高かったことが示されました。例えば、男性のベジタリアンの平均腸の運動回数は10.5回であり、女性は9.1回でした。また、食物繊維や非アルコール性飲料の摂取量が増えると、腸の運動頻度も増加する関連性が見られました。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14972075/
そのパワーを活かした、「自宅で出来る&お腹が減らない」最強のハーブファスティングもオススメなので、興味があれば参考にしてみてください。