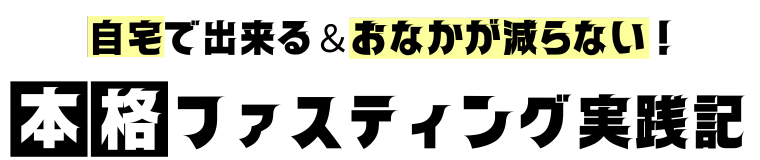ウコンは東南アジアを中心に分布している多年草植物で、沖縄では古来から、身体の調子が出ないときや疲れているときに飲まれて来ました。
現在、欧米ではウコンの心疾患や能疾患などに対する効果、そして抗ガン作用も注目されています。
この記事では、そんなウコンの
- 効果
- 副作用
- おすすめの楽しみ方
について、ハーブを使った最強ファスティングを定期的に実践しているハーブマニアがまとめてみました。
さらにウコンの育て方や、ハーブティーを美味しく飲むためのポイントについてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!
ウコンの基本情報

| 名称 | ウコン(秋ウコン) |
| 英名 | turmeric |
| 学名 | Curcuma longa Linne |
| 和名 | ウコン(鬱金、欝金、宇金、玉金) |
| 分類 | ショウガ科ウコン属ウコン |
| 原産地 | インド、南アジア |
| 主要成分 | クルクミン、デメトキシクルクミン、ビスデメトキシクルクミン、フラボノイド |
| 使用部位 | 根、茎 |
| 代表的効能 | 抗酸化作用、抗炎症作用、肝保護作用、消化不良改善、間接リウマチ改善、美肌効果 |
| 利用法 |
その他着色料、染料など |
英名でターメリックと言われるウコンは、カレーの黄色い色の元になっているスパイスとして、知っている人も多いのではないでしょうか。
現在、世界中で約50種類のウコンがあると言われており、日本でウコンとされているのは、春ウコン、秋ウコン、紫ウコン、黒ウコンの4つです。
料理の際のスパイスとして用いられることが多いウコンですが、古くからアーユルヴェーダなど医療に利用されており、現在でも漢方やサプリメントとして利用されています。
ウコンの効果・効能・作用を解説
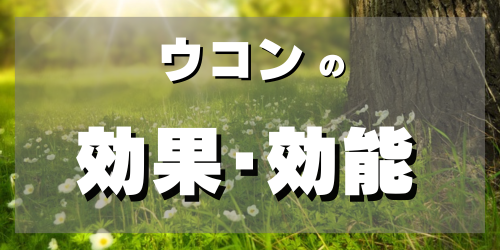
カレーの黄色い色でおなじみのウコンは、私たちの身体にいい影響を与える成分をたくさん持っています。
この記事では、主にその中でも黄色の色素成分であるクルクミン (curcumine)の持つ、二日酔い防止効果、認知症予防効果、抗ガン効果の3点について解説します。
効果①:二日酔い防止効果
ウコンに含まれるクルクミンという成分には、肝臓からの胆汁の分泌を促進させ、二日酔いの原因となるアセトアルデヒドの分解を促進させる働きがあると言われています。
また、肝臓を保護し、肝障害や肝硬変を抑制する働きがあるとも言われています。
沖縄では、ウコンは古くから二日酔い防止の薬として、民間療法の中で用いられてきました。
効果②:認知症予防効果
ウコンに含まれるクルクミンは、適量を摂取することで、アルツハイマー病の原因となる、アミロイドβというタンパク質が、脳に沈着することを抑える働きがあると言われています。
また、クルクミンの持つ優れた抗酸化作用は細胞の老化を抑え、認知症の予防に繋がります。
事実、ウコンを豊富に摂取するインドでは、アルツハイマー病の患者数がアメリカの約4分の1と言われています。
効果③:抗ガン作用
ウコンに含まれるクルクミンには、ガンの原因となる活性酸素の働きを抑える効果があると考えられています。
オレゴン州立大学ライナスポーリング研究所のWebサイトによると、クルクミンは、大腸がん、胃がん、口腔がん、肝臓がんについて抑制作用があるとの動物実験結果が出ています。
近年では、クルクミンを利用した、副作用がない抗ガン剤が研究されています。
効果④:その他
上記で述べた3点の効果の他にも、ウコンには、その精油成分による抗菌・抗虫効果があり、それゆえ、ウコン染めの布が産着や風呂敷として用いられてきました。
また、近年では美肌効果にも注目が集まっており、ウコンの持つ様々な効能は、これから今以上に注目を集めて行くことでしょう。
ウコンの副作用や注意事項、禁忌など
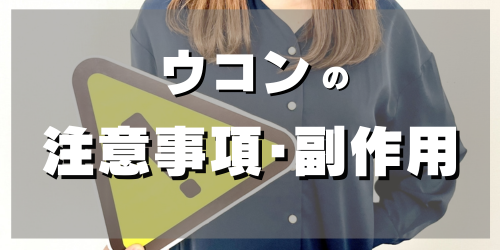
ウコンにはミネラル分が多く含まれています。
非アルコール性脂肪性肝炎やC型肝炎の方は、ウコンを摂取するとミネラル分の内、鉄分が身体の中に蓄積され、症状が悪化する可能性がありますので、摂取は控えましょう。
また、ウコンには胆嚢を刺激する作用があるため、胆石の方は摂取を控えましょう。
基礎疾患のない方は、通常摂取量であれば問題はありませんが、過剰摂取した場合肝臓の働きが過剰になり、それが肝臓の機能低下の原因となるため、過剰な摂取は控えましょう。
ウコンに含まれる精油成分には子宮を収縮させる働きがあるため、妊娠中の方は摂取を控えましょう。
その他、ウコンを摂取すると、まれに皮膚がかゆくなる等のアレルギー症状が出る場合があります。
ウコンのハーブとしての使い方
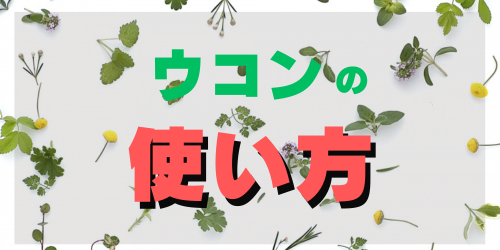
ウコンは、主にカレーなどの香辛料として知られていますが、ハーブティーやサプリメントとしても利用されています。
ハーブティー

ウコンのハーブティーを作るには、ターメリックパウダーを使用します。
<ハーブティーの作り方>
- 急須またはポットに、ターメリックパウダー小さじ半分を入れ、400mlのお湯を注ぐ。
- 約2分蒸らす。
- ターメリックが底に沈んだ後、ターメリックが入らないようにそっとカップに注いで完成。
ウコンのハーブティーは、苦味がありクセがあります。
もし飲みにくいと感じたら、ジンジャーやミルクをブレンドしたり、蜂蜜やレモン果汁を加えてみると、飲みやすくなるかもしれません。
サプリメント

ウコンのサプリメントは、健康補助食品として、ネット通販サイトやドラッグストアで販売されています。
ただ、ウコンは非アルコール性脂肪性肝炎やC型肝炎の方、胆石がある方、妊娠中の人は副作用が生じる可能性があるため、飲用することを避けましょう。
もし服用することに不安がある場合は、事前に医師に相談することをおすすめします。
スパイス

ウコンはカレーのスパイスとしてだけでなく、他の料理にも使用することができます。
沖縄料理のタコライスやドリア、野菜炒めなどの料理のスパイスとして使用するほか、ジンジャーブレッドクッキーのような要領で、ウコンをクッキーに混ぜるとピリッといいアクセントになります。
料理からお菓子まで、アクセントをつけたい時におすすめです。
ウコンのよくある質問

ウコンについて、よくある質問を調べてまとめてみました。
ウコンは乾燥と寒さに弱く、東北地方北部地域以北では育たないと言われていますが、それ以外の日本の幅広い地域で育てることが出来ます。
ウコンの植え付けに適した季節は3月下旬~5月上旬頃です。
ショウガのような形の「種ウコン」を、新芽が3~4個付くよう切り分けた上で、それぞれの株の感覚を30~40cm空け、深さ5~7cmに植えて土をかぶせます。
水はたっぷりとやると共に、植え付けから2カ月ほどしたら追肥をし、それから2カ月したら、また追肥しましょう。
ウコンは水はけの悪い土では育たないので、腐葉土などを混ぜたふかふかの土を使いましょう。
10月半ば~11月になり、葉が枯れ始めたら収穫の時期です。
霜が降りる前に収穫しましょう。
収穫した根茎は、泥を洗い落した後、薄く包丁で輪切りにして2~3日干してから薄くスライスし、乾燥後ミキサーなどで粉砕した後、粉末にしてから保存します。
ウコンの歴史は古く、5,000年前に起源を発するインドの伝統医学 「アユールヴェーダ」には、既にその名が記載されています。
人間による栽培が始まったのは、おそらく古代メソポタミア文明における、ソロモン王時代(紀元前970~931年)ごろからであろうとされています。
その後、ウコンの栽培方法は、メソポタミアを経てパレスチナ方面へと伝わりました。すでに紀元前700~600年代には、ターメリックが着色用のスパイスとして用いられていることが記録されています。
古代ローマにも、ウコンはギリシャ経由で紀元前1世紀ごろ伝えられました。フランスでは、ターメリックがサフランに代わる安価なスパイスとしてスパイスとして用いられました。アジアでは調味料、着色料、医薬として今日まで用いられています。
ウコンは日本にも古くから伝わり、平安時代に編纂された「本草和名」でも、「鬱金」の記載を見ることができます。しかしながら、本格的に栽培が開始されたのは、室町時代の沖縄においてだと考えられています。
ウコンは当時大変貴重な植物で、琉球王府の重要な財源とされていました。今でも沖縄ではとても嗜まれており、ウコンの輸入量が一番多い都道府県は沖縄県です。
ウコンというと粉末状を思い浮かべることが多いと思いますが、生でも食べることができます。
生姜のように生のウコンをすりおろしてポテトサラダに入れたり、生ウコンを甘酢漬けにしたりと様々な楽しみ方ができます。
ただ、生のウコンは苦味が強いので、生で使用する際は使用する量に注意しましょう。
まとめと研究情報
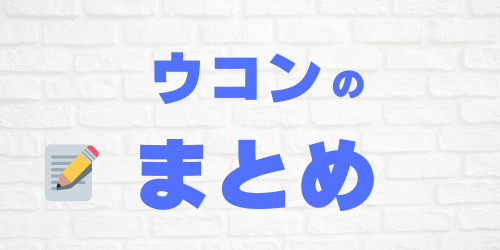
ウコンは、カレーの香辛料としてだけでなく、ハーブティーやお菓子の材料としても使用することができ、私たちの体に良い影響を与えてくれる成分を多く含んでいます。
ただ、妊娠中や胆石があるなど、使用に注意が必要になる場合があります。
ウコンを、安全かつ効果的に日常生活に取り入れていくためにも、この記事をよく読んで参考にしてくださいね。
おさらい
<効果・効能・作用>
- 二日酔い予防効果
- 認知症予防効果
- 抗ガン効果
<副作用・禁忌・注意点>
- 子宮を収縮させる可能性があるため、妊娠中の使用は避ける
- 非アルコール性脂肪性肝炎やC型肝炎の方は、症状が悪化する可能性があるため摂取を控える
- 胆石がある場合は胆嚢を刺激する可能性があるため、使用を避ける
<使用方法>
- ハーブティー
- サプリメント
- スパイス
研究情報
下記の研究データ、エビデンスを参考にさせて頂きました。
ウコンの肝臓の保護作用
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22452372
II型糖尿病の合併症である肝臓の繊維化について、ウコンに含まれるクルクミンが試験管内で肝星状細胞の活性化を抑制し、AGE受容体の働きを抑制し、また抗酸化酵素のグルタチオンの働きを活性化させることで、肝臓を保護する作用があるとし、II型糖尿病の肝臓の繊維化を抑制する可能性があることが示唆されました。
ウコンの消化不良改善効果
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2699615
消化不良がある人を対象にウコンカプセル1日2g を7日間摂取させた群とプラセボ群を比較したとろこ、摂取した群の約87%の人の消化不良に改善が見られたことから、ウコンには消化不良改善効果があることが示唆されました。
そのパワーを活かした、「自宅で出来る&お腹が減らない」最強のハーブファスティングもオススメなので、興味があれば参考にしてみてください。